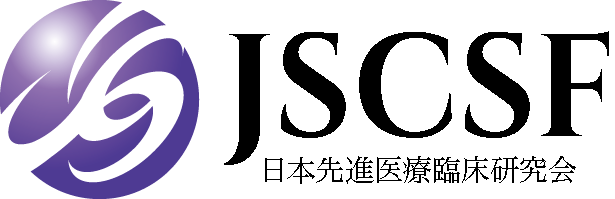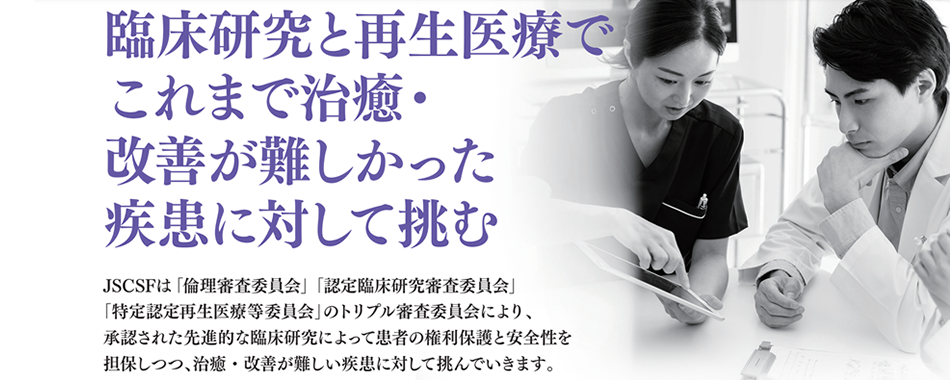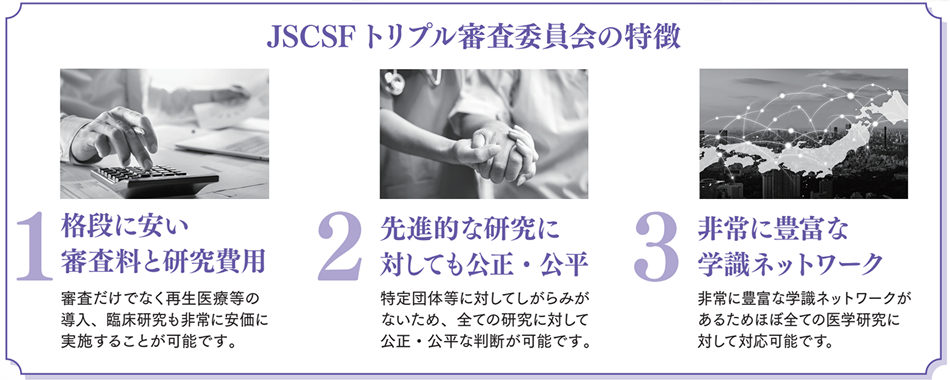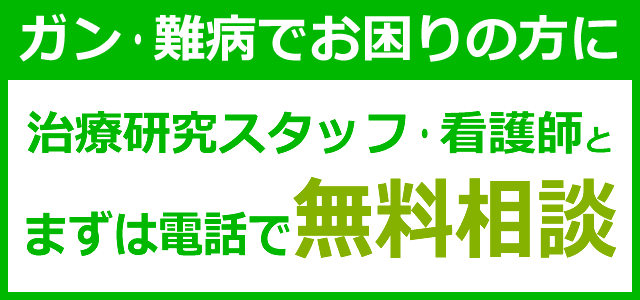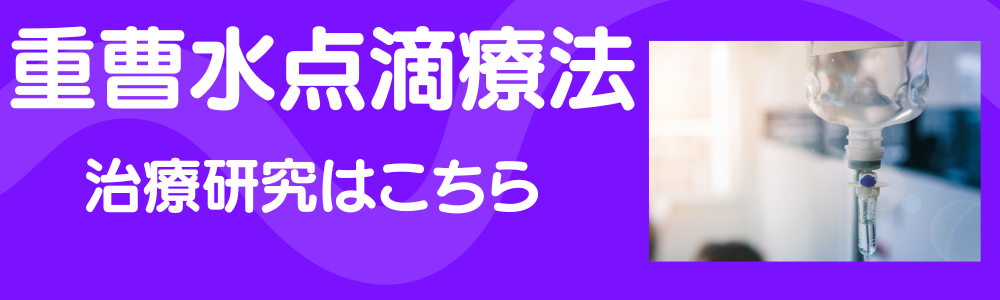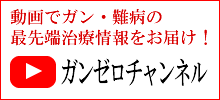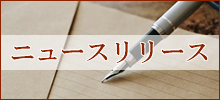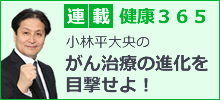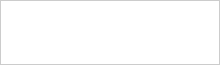日本先進医療臨床研究会(略称JSCSF:Japan Society of Clinical Study for Frontier-Medicine)について
 一般社団法人日本先進医療臨床研究会(略称JSCSF::Japan Society of Clinical Study for Frontier-Medicine)は、「世界からガンと難病と老化と感染症をなくし、健康長寿・生涯壮年!120歳で現役の世界」を目指して、医師・歯科医師を中心に、医療従事者、医療関連企業、健康関連企業、研究者、志ある一般の方たち、から構成される研究会です。
一般社団法人日本先進医療臨床研究会(略称JSCSF::Japan Society of Clinical Study for Frontier-Medicine)は、「世界からガンと難病と老化と感染症をなくし、健康長寿・生涯壮年!120歳で現役の世界」を目指して、医師・歯科医師を中心に、医療従事者、医療関連企業、健康関連企業、研究者、志ある一般の方たち、から構成される研究会です。
現在の標準的な治療法では完治が難しい疾患に対して、最先端医学の知見から、伝統療法、民間療法まで、様々な治療法や、その組み合わせを、医師と患者の同意のもとでの実臨床で効果を試し、症例報告の集積によって、治癒・改善・再発防止・予防の効果を検証しています。
当会の歩み
当会は、2008年2月に、標準的な治療法では完治が難しい進行ガンや難病に苦しむ患者の救済を目指す先進的な医師たちの意見交換会として発足しました。
当会はその後「統合医学医師の会」の名称で、およそ7年に渡り、1~2ヶ月に1度の症例報告や意見交換会を開催してきました。
当会では、その後、進行ガンや難病を治癒できる可能性を秘めた先進的な治療法のいくつかと出会ったことで、それらの治療法を、全国の医師を通して日本中に広げるべく、2015年5月に、「一般社団法人日本先進医療臨床研究会」と改名し、発展的な拡大を開始致しました。
当初は「世界からガンと難病をなくす!」というテーマを掲げて活動しましたが、現在はガンと難病に加えて、感染症と老化をなくすことも視野に入れて活動してます。
また、従来の会員医師による治療結果の積み上げ研究に加えて、この程、厚生労働省から認定を受けた2つの審査委員会にて、臨床研究、特定臨床研究、再生医療など、更に先進的な治療方法にも積極的に挑んで参ります。
今後も、最先端医学の知見から伝統療法、民間療法まで様々な治療法やその組み合わせを、医師と患者の同意のもとでの実臨床で効果を試し、それら治療や研究の成果によって、ガンと難病と感染症と老化に苦しむ人を救い、またそれらの方法を世界に向けて発信するために活動して参ります。
皆様のご協力を何卒よろしくお願いいたします。

統合医学医師の会発起人:故・高原喜八郎先生(前列左から2番目)、名誉会長:帯津良一先生(前列右から2番目)、初代会長:阿部博幸先生(前列1番右)ほか
理論医学とSBMについて
「理論医学」は、標準的な保険診療では完治が難しいとされる疾患に対して、症例実績と科学的な考察にに基づく「SBM(ScienceBased Medicine)」の手法によって検証された治療法や自然療法、東洋医学、民間療法など多用な治療を併用することで治癒=完治を目指す治療法です。
「理論医学」は当会顧問・新井圭輔先生が提唱する治療法です。新井圭輔先生は科学的考察による治療の取り組み(SBM)を「理論医学」と呼び、これまでのEBM(Evidenced Based Medicine)=「統計に基づく治療」に基づく治療法を「経験医学」と呼びます。また、SBM(Science Based Medicine)=「科学的考察に基づく治療」は当会初代理事長・白川太郎先生や多くの会員医師が実践する科学的な考察に基づく治療法でもあります。
→ 複合寛解療法(SBMと理論医学)について
臨床研究審査委員会の設置
当会ではこれまで、臨床研究法(2017年4月14日公布、2018年4月1日施行)における「臨床研究」及び「特定臨床研究」には該当しない「会員医療機関での治療結果を集積する症例研究(文書研究)」を主に行ってきました。そのため、当会内に設置した倫理審査委員会(IRB;Institutional Review Board)によって、実験的な治療の対象となる患者の権利保護と安全性の確保の観点から倫理審査を行ってきました。
しかし昨今の遺伝子学や細胞培養技術などの急速な進歩により医師主導の臨床研究や、企業発案型の特定臨床研究など臨床研究法や再生医療法など法律によって制限される研究を行う必要性が増大しており、それらの研究に対応するため、当会でも法律によって規定され、厚生労働省よりの認可を受けて審査を行う「認定臨床研究審査委員会(CRB;Certificational Review Board)」を設置することと致しました。
なお、現行の「倫理審査委員会(IRB;Institutional Review Board)」については、これまで通り、引き続き疫学研究(資料研究)や文書研究(症例報告の集積研究)など、介入を伴わない研究に関して審査を行って参りますので、よろしくお願いいたします。
※「認定臨床研究審査委員会」に関して詳しくは下記ページをご覧ください。
https://jscsf.org/crb
※「倫理審査委員会」に関して詳しくは、下記ページをご覧ください。
https://jscsf.org/irb
再生医療等委員会の設置
現在の標準的な治療法で治癒・改善が望めない多くの疾患に対して、大きな期待をされている治療法に「再生医療」があります。再生医療は担当医師や医療機関による高い倫理観や高度な管理能力などが求められる医療であるため、再生医療を行うためには厚生労働省によって認可された「認定再生医療等委員会」「特定認定再生医療等委員会」での審査及び承認が必要となります。
わが国では再生医療を推進するため、2014年11月に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号、以下、再生医療法)」と、薬事法等を大幅に改正した法律である「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)」が施行されました。
再生医療法は、再生医療等の迅速かつ安全な提供や普及の促進を図ることを目的としており、再生医療等を臨床研究や自由診療として行う場合は、再生医療法の対象となり、再生医療法の施行後に臨床研究法が施行されましたが、再生医療は臨床研究法だけでなく再生医療法も同時に遵守することが必要です。そのため再生医療を伴う研究を行う場合には、上記の「認定臨床研究審査委員会」だけではなく、「認定再生医療等委員会」、または「特定認定再生医療等委員会」の承認も受ける必要があります。
再生医療法では、医療機関が再生医療等を提供しようとするときに遵守しなければならない事項を定めており、再生医療法の対象となる再生医療等は、医療のリスクに応じて第1種、第2種、第3種再生医療等技術に分類されています。どのリスク区分に分類された場合であっても、厚生労働省または地方厚生局へ再生医療等提供計画の提出が必要で、再生医療等提供計画は厚生労働省へ提出する前に、第1種および第2種再生医療等については「特定認定再生医療等委員会」の、第3種再生医療等については「認定再生医療等委員会」の意見を聞き、厚生労働省の審査・承認を受けることが必要とされています。
再生医療のリスク分類については、第1種再生医療等は、iPS細胞や遺伝子を導入する操作を行った細胞を用いるもの、または投与を受ける者以外の人の細胞を用いるもの等が該当し、第2種再生医療等には、培養した幹細胞を利用したもの等が該当し、第3種再生医療等には、ガン免疫治療等でリンパ球や血小板等を用いるもの等が該当すると定められています。
当会では、現行の標準治療では治癒・改善が望めない様々な疾患に対して期待が大きい再生医療に関しても、今後注力していくため、第3種の再生医療等計画を審査できる「認定再生医療等委員会」だけでなく、第1種・第2種の再生医療等計画を審査できる「特定認定再生医療等委員会」の認可も同時に取得しました。
当会理事・顧問、会員の先生方におかれましては、新たに設置されました「認定臨床研究審査委員会」「再生医療等委員会」「特定認定再生医療等委員会」をご活用頂き、患者の権利保護と安全性を担保された先進的な治療によって、これまで治癒・改善が難しかった疾患に対して挑んで頂きたいと考えています。よろしくお願い申し上げます。
※「認定再生医療等委員会」「特定認定再生医療等委員会」に関して詳しくは、下記ページをご覧ください。
https://jscsf.org/rmc